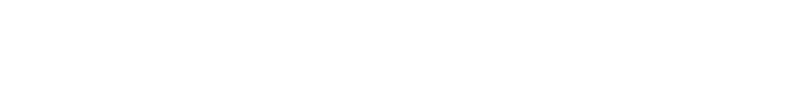お知らせ
【特集】不動産価格はいつまで上がる? 2026年以降の「市場展望」と「価格上昇の3つの要因」

不動産投資を検討されている人の多くが、「今の価格は高すぎるのではないか」「バブルのようにいつか暴落するのではないか」という不安を抱えています。
結論から申し上げますと、現在の不動産価格の上昇は、1990年前後のバブル期のような過熱した投機によるものではなく、供給側のコスト増に裏打ちされた「構造的な上昇」です。つまり、待っていれば以前のような水準まで下がるというシナリオは、現在の経済環境下では極めて考えにくいといわざるを得ません。
本記事では、2026年以降の市場展望を見据え、なぜ不動産価格が下がりにくいのか、そして「買い時」を待つことがどのような経済的リスクを招くのかについて、税務と財務の視点から客観的に解説します。
現在の不動産価格上昇を牽引している要因

現在の不動産価格、特に都市部の新築マンション価格が上昇し続けている背景には、一時的な流行ではなく、供給サイドにおける「3つの深刻なコスト増」があります。これらは不動産会社が利益を削って対応できるレベルを超えており、分譲価格への転嫁が避けられない構造になっています。
1.建築資材の歴史的な高騰
第一の要因は、世界的なインフレと円安に伴う建築資材価格の上昇です。 鉄筋、コンクリート、住宅設備機器などの主要資材は、ここ数年で数段階の価格引き上げが行われました。国土交通省が発表する「建設工事費デフレーター」を見ても、建築コストは右肩上がりで推移しており、過去の安価な時代には戻れない地点に達しています。一度上がった資材価格や製造エネルギーコストは、デフレ期のような急激な下落は見込みにくく、これが物件価格の下限を押し上げています。
2. 人件費の上昇と「2024年問題」
第二の要因は、深刻な人手不足に伴う人件費の上昇です。 建設業界では、2024年4月から施行された「時間外労働の上限規制(いわゆる2024年問題)」により、現場の労働環境改善が急務となりました。これは働く側にとっては望ましいことですが、発注側から見れば「工期の長期化」と「さらなる労務単価の上昇」を意味します。若年層の入職者減少もあり、熟練工の確保には高いコストがかかるようになっています。税務上の原価計算においても、労務費の割合は年々増加しており、これが販売価格を押し上げる強力な圧力となっています。
3.用地取得の困難化
第三の要因は、都心部における開発用地の枯渇と取得価格の高騰です。 特に利便性の高い都心エリアでは、マンションを建てられるまとまった土地が極めて稀少になっています。数少ない優良な土地を巡って、大手デベロッパー同士が競り合う構図が続いており、土地の仕入れ価格は高止まりしています。また、再開発プロジェクトに組み込まれるケースも多く、土地代そのものが下がりにくい環境が整ってしまっています。
以上の通り、供給側の「材料費」「人件費」「土地代」という3要素すべてが上昇しているため、新築マンションの供給価格が下落するためには、これらの構造そのものが崩れる必要があります。しかし、現状の日本経済においてその兆しは見当たりません。
「買い時」を待つことがリスクになる可能性

「もう少し価格が落ち着いてから始めよう」と考えるのは自然な心理です。しかし、財務的な視点で見ると、この「待ち」の姿勢が、実は最も大きな機会損失(目に見えない損失)を生んでいる可能性があります。
ローン完済時期の遅延という「時間的リスク」
不動産投資の最大の武器は「長期のローンを活用したレバレッジ」です。一般的に、金融機関は完済時の年齢に上限(多くは75歳〜80歳)を設けています。 たとえば、現在35歳の人が35年ローンを組めば、70歳で完済を迎え、その後の家賃収入はすべて純粋な老後資金となります。しかし、「価格が下がるまで」と5年待って40歳で開始した場合、完済は75歳になります。この5年の差は、定年後のキャッシュフロー計画に甚大な影響を及ぼします。不動産投資において「時間」は最も重要な資産であり、スタートを遅らせることは、その分だけ資産形成の効率を下げていることと同義なのです。
インフレ下での現金保有リスク
現在、日本は長らく続いたデフレを脱却し、インフレ(物価上昇)局面に入っています。インフレ下では「現金の価値」が目減りし、「モノ(資産)の価値」が相対的に上がります。 税理士の視点で見れば、インフレ局面で借入金(固定負債)を利用して資産を持つことは、非常に理にかなったヘッジ戦略です。借入金額は固定されていますが、物価上昇に伴い家賃や物件価格が上昇すれば、実質的な借金の負担感は軽減されます。逆に、価格が下がるのを待って現金を銀行に寝かせている間、その現金の購買力は日々低下している可能性があるのです。
支払う家賃は「掛け捨て」のコスト
投資用マンションを購入せず、賃貸住宅に住み続けながらチャンスを待つ場合、その期間中に支払う家賃は1円も資産になりません。年収700万円以上の層であれば、年間150万円〜200万円程度の家賃を支払っている人も多いでしょう。5年待てば約1,000万円の支出です。この金額は、物件価格が1,000万円下落しない限り取り戻せない「コスト」となります。現在の市場環境で、都心の物件価格が5年で1,000万円も暴落する確率は、構造的な要因を考えれば極めて低いといわざるを得ません。
資産価値が維持されるエリア・物件の見極め方

不動産価格全体が上昇している今だからこそ、何でも買えばよいというわけではありません。これからの市場は「二極化」がさらに進みます。価値が維持される物件と、そうでない物件の差は、これまで以上に明確になります。
都心回帰と「職住近接」のニーズ
少子高齢化が進む日本において、資産価値を維持するための絶対条件は「需要が絶えない場所」であること。 リモートワークが普及したとはいえ、年収の高いビジネスパーソンが集まるのは依然として都心部です。千代田区、中央区、港区の都心3区に加え、新宿区、渋谷区、品川区といったエリアは、圧倒的な就業人口を背景に賃貸需要が極めて安定しています。これらのエリアでは、将来的に売却を検討する際も買い手が見つかりやすく、キャピタルゲイン(売却益)を狙わずとも、安定したインカムゲイン(家賃収入)によって資産の目減りを防ぐことができます。
「駅徒歩5分圏内」の希少性
区分マンション投資において、駅からの距離は資産価値に直結します。 特に、都心部かつ「最寄り駅から徒歩5分以内」の物件は、供給量が限られているため、経年による価格の下落幅が非常に小さいというデータがあります。建物自体は年数が経てば償却され価値が下がりますが、その利便性という「立地価値」は変わりません。むしろ、周辺の再開発などによって価値が向上することすらあります。
単身世帯・DINKS向け「コンパクトマンション」
20代〜40代の現役世代がターゲットとなる区分マンション投資では、将来の世帯構造の変化も予測しておく必要があります。 東京都心の単身世帯数は増加傾向にあり、今後もコンパクトな1Kや1LDKの需要は底堅いと予想されます。一方で、郊外の広いファミリー向け物件は、人口減少の影響を直接的に受けやすく、将来の出口戦略(売却)においてリスクを孕みます。投資として考えるならば、流動性が高く、常に一定の居住ニーズが見込める都心部のコンパクトマンションを選択するのが、財務の安定性を高める鉄則です。
まとめ
2026年以降の不動産市場を展望すると、建築コストの増大や人手不足といった構造的な要因により、都心部の物件価格が以前のような安値に戻る可能性は極めて低いといえます。
こうした環境下で重要となるのは、目先の価格の上下に一喜一憂することではなく、自身のライフプランに基づいた「資産の組み換え」をいかに早く始めるかという視点。不動産投資は、他人資本(銀行融資)を活用しながら、時間を味方につけて資産を築くモデルです。
年収700万円を超えるビジネスパーソンにとって、不動産は単なる投資対象である以上に、インフレ対策や老後資金の確保、そして所得税の還付といった財務戦略上の重要なツールとなり得ます。価格上昇の背景にある真の要因を理解し、冷静に「負けないエリア」を見極めることができれば、今の市場環境は決して「高すぎる」ものではなく、将来の安定に向けた正当な入口となるでしょう。
<著者プロフィール>
長岡 理知
長岡FP事務所合同会社 代表社員
2005年大手生命保険会社に入社。2009年より大手住宅メーカー専属FPとして家計相談業務をスタート。住宅購入時の相談は累計3500世帯を超える。2020年に保険会社を退職し、住宅専門の独立系FP事務所を設立。住宅を購入する時の予算決めと家計分析、リスク対策を専門業務とする。建物の構造・仕様・施工品質による維持費の違いや寿命に着目し、安易な建物価格での比較に警鐘を鳴らしている。
株式会社 青山メインランド
代表取締役 西原良三